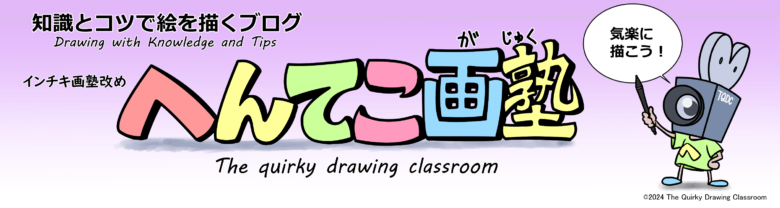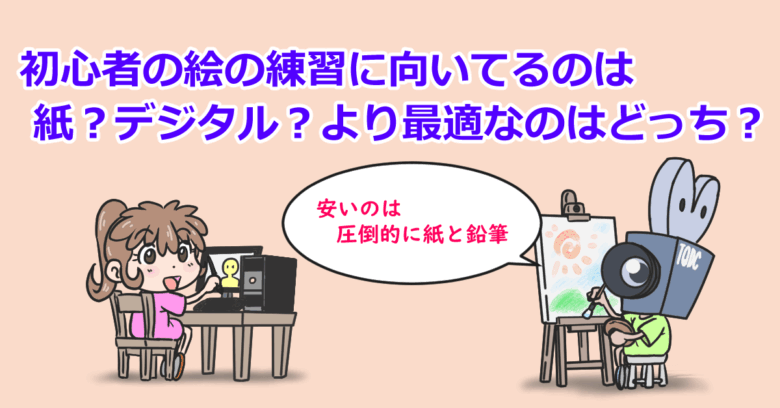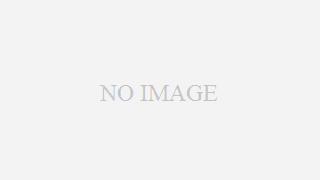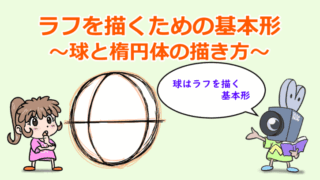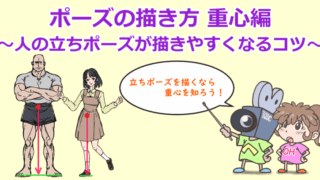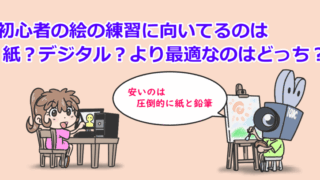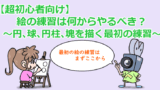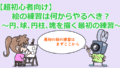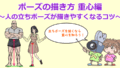《初心者~初級者向け》
ひと昔前まで、「絵を描く」となると絵筆や鉛筆を持って紙に描くのが当たり前でしたが、この10年ほどでスマートフォンやタブレットを使って絵を描くことが広く定着して来ました。
デジタルの作画ツールはとても便利な道具ですが、「初心者が絵を描き始める」時により適しているのはどちらでしょうか?
今回の記事では、実際に紙(アナログ)とデジタルを使って絵を描いている経験から、初心者により最適な作画ツールについて考えてみたいと思います。
▼前回の記事はこちら
※本ブログの記事には広告が表示されます。
今回の記事の内容
今回の記事の内容です。
絵の練習により適した道具について、実際に両方の道具を仕事で使って来た経験から考えてみます。
特に「これから絵の練習を始める」という初心者の人はどちらの道具から始めた方がよいのかについて考察してみます。

絵を描こうと思ってるんだけど、デジタルで始めるべき?それとも紙と鉛筆とかのアナログの方が良いのかなぁ?
というような悩みを持っている人には参考になる記事かと思います。
デジタルツールとアナログツール
まず最初にこの記事において「デジタル作画ツール」とは何を指し、「アナログ作画ツール」とは何を指すのかについて説明しておきます。
デジタル作画ツール

デジタル作画ツールとは、上の写真にもあるような板タブレットや液晶タブレット、スマホなどのデジタル入力ツールと作画アプリを使って絵を描くやり方です。
絵を描くのに紙や鉛筆はもはや必要なく、カラーで絵を描くために大量の絵の具も必要としません。
ただし、電気がないと使えませんし、仕事で使っている最中に壊れたりしたら半泣きです。
しかし、まぁそんな事態にはほとんどならないのでとても便利な道具だということは間違いないです。
また、最近はAIを使って生成されたイラストなどもよく見かけます。
AIイラストもデジタルで作画されたものですが、今回の記事ではあくまで「人の手によって描く」ことを前提とするので、AIによる作画は含みません。
アナログ作画ツール

アナログの場合はツールと言うよりも「道具」と言った方がしっくりきます。
何千年もの時間、人間はアナログの道具を使って絵を描いてきました。
土の地面と棒っきれがあれば絵は描けますが、この記事中の「アナログ作画ツール」は紙と鉛筆やペンなどの筆記具を指すこととします。
デジタルツールのメリット
では、デジタル・アナログそれぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。
まずはデジタル作画用のツールからです。
アナログにはできない多彩な機能
アナログ作画でできることはとても増えました。
個人的にはUndo(アンドゥ)、Redo(リドゥ)機能がデジタル作画の一番のメリットと感じています。
絵を描くということは試行錯誤のくり返しですが、その過程で描いては消すという作業を何度もおこなうことになります。
そういったことをくり返していると「一回前に描いた線の方が良かったな…」ということが必ずおこります。
紙と鉛筆であれば、その線を消しゴムで消してしまっていたらそれで終わりです。
しかし、デジタルなら簡単に前の状態に復元することができます。
これは絵を描く上では便利極まりない機能です。
デジタル作画に慣れてくると、紙で描いている時でも「Ctrl+Z」を押したくなります。
そして、「アナログだった…」と絶望するのです。
それ以外にも、デジタルツールには鉛筆やペン、筆など色々な作画道具、ほぼ無限の組み合わせが可能な絵の具、さらには描く紙の質感まで選択できる幅広い機能が収まっています。
デジタルの作画デバイスとアプリさえそろえれば、イラストだろうが漫画だろうが、水墨画だろうがどんな種類の絵だって描くことができます。
どこでも描ける手軽さ
さらにデジタルツールはとても使い勝手が良いというメリットもあります。
PCと液晶タブレットをつなげて…という本格的なデジタル作画はまた別として、スマホと指を使って、いつでもどこでも簡単に絵を描くことができます。
これは絵の練習をする際にも便利でしょう。
街中で「ちょっとクロッキー」ということも簡単にできます。
アナログだとクロッキー帳を出して、鉛筆を出して…とハードルが高くなります。
描きたい時に描けるというのはデジタル作画の大きな魅力です。
デジタル作画のデメリット
デジタルツールはとても便利な道具ですが、反面デメリットも大きいです。
初期コストが高い
これは一番わかりやすいデメリットでしょう。
以前に比べて値段は下がって来てはいますが、デジタルの作画ツールは高価です。
板タブの安いものでも数千円、液タブなら数万円から10万円以上するものもざらにあります。
これに加えて作画のアプリも必要です。
無料のものもありますが、作画ソフトとしてメジャーなCLIP STUDIOであれば、安価なもので数千円、上位グレードのものなら数万円します。
一番安くそろえても5千円から1万円程度、良いものを買いそろえたら5万円から10万円以上の出費になってしまうでしょう。
これは絵を描き始める初期費用としてはかなり高額です。
特に初心者の人が勢いだけでデジタル作画用のツールを買いそろえるのは考えた方が良いでしょう。
良い機材を買ったけど、ずーっとタンスの中に眠ったままという話もよく聞きます。
初心者にはハードルが高い
そして、デジタル作画ツールは初心者にはややハードルが高いです。
デジタル作画ツールは「ある程度絵が描けて知識も持っている人が使う」ということが前提になっているところがあります。
メリットのところでも描きましたが、デジタルはとにかく機能が多彩です。
機能が多いので、何でもできる反面、何から始めたら良いのかという壁にぶつかることになります。
自分がどういった機能を使って、どういった作品を描きたいのか、ということがある程度決まっていないと、逆に機能の多さにとまどってしまうことになるでしょう。
デジタルは少し絵を描き慣れてきて「デジタルのこの機能を使ってこういう絵が描きたい」という方針が定まってから手を出す方がスムーズに使えるかも知れません。
拡大縮小ができる
デジタルは紙に絵を描く場合と違って、キャンバスを拡大縮小しながら描くことができます。
拡大縮小は一見便利な機能なのですが、ちょっと厄介な面も持っています。
それは、どこまでも拡大して表示できるので絵の全体像が把握しにくいという点です。
拡大しながら描くと線も描きやすいのですが、ある程度描いて縮小してみたら、デッサンが大きく崩れていたということがおきます。
縮小してデッサンの間違いに気付ければ良いですが、初心者の人ではそれに気付かないこともあるでしょう。
初心者が「絵を見る目」を育てていくプロセスとしては、「絵の全体像を確認しながら描く」というやり方がかかせません。
全体を見ることでデッサン的な間違いを見極める目の力が育ってきます。
そういう点では拡大縮小機能を持つデジタル作画ツールは「絵を見る目」が育ちにくいと言えます。
「デジタルでも拡大させずに描けば良いのでは?」と思うかもしれませんが、便利な機能ですし、デジタル作画に使うモニターは総じて小さめなので、ついつい拡大して描いてしまうのです。
サポート機能が多すぎて「描く力」がつきにくい
これは使う作画アプリの種類にもよりますが、最近のデジタル作画ソフトは絵を描くためのサポート機能がとても充実しています。
3Dのモデル人形や描くのが難しい手のサンプルモデル、パース定規などなど、必要なものを必要に応じて使用して絵を描いていくことができます。
これもとても便利な機能ですが、本来の「描く力」を身につけたいのであれば大きなデメリットにもなりえます。
サンプルを下に敷きながら描くと描きやすいと思いますが、それはトレースしているのとほとんど変わらず、「描く力」を獲得したことにはなりません。
自分で描くことを目指すのであれば、デジタル作画ツールの過剰なサポート機能は、それを阻害するものにもなり得るでしょう。
アナログ作画のメリット
続いてアナログツールを見ていきます。
はじめるハードルの低さ
紙や鉛筆などのアナログ作画の一番のメリットは、始めるハードルの低さでしょう。
描こうと思えば、いつでも描き始めることができます。
わざわざ画材屋さんに足を運んで道具を買いそろえなくても、学校で使っている鉛筆やシャープペンシルを使って、チラシの裏に描き始めるいうこともできます。
手元にある道具で始められるというのはコストの安さでもあります。
家に紙と鉛筆があればほぼ0円で、気合を入れて新たにスケッチブックと鉛筆を買ったとしても数百円から千円程度の出費で済むでしょう。
初期費用の安さは、描くのをやめてしまった時のダメージも軽いです。
しばらく続けてみて、「このまま継続して描けそうだ」となったら、次の道具を描くことを考えれば良いのです。
最初からデジタルツール一式を買いそろえてしまって、結局描きませんでした…というのは、お財布と心へのダメージが大きすぎます。
「見る目の力」がつきやすい
紙と鉛筆で描くことは、絵を見る目を確実に育ててくれます。
紙は常にその大きさが最大サイズです。
デジタルのように拡大も縮小もできません。
常に絵の全体像を視野に入れながら描く作業ができます。
このことによってデッサン的な崩れなど、絵の間違っているところに気付きやすくなります。
絵を見る力をつけるのであれば紙と鉛筆が一番です。
アナログ作画のデメリット
人類が何千年と絵を描く手段としてきたアナログ作画ですが、もちろんデメリットもあります。
作画に手間がかかる
アナログは「やり直し」という行為がしにくいです。
一度描いた線を消してしまえばそれまでです。
デジタルのようにショートカットひとつでもとに戻すということができません。
さらに一度描いてみて、「やはり人物を右に数ミリずらした方がバランスが良い」となった時の調整もかなり大変です。
デジタルなら対象となるレイヤーを少し動かしてやれば済むことですが、アナログだとそうもいきません。
たいていの場合はイチから描き直すことになるでしょう。
絵の左右反転や透過率の調整など、デジタルなら簡単にできる操作もアナログでは難しいです。
デジタル作画に慣れると、アナログで絵を描くことはとても手間がかかると思えてしまいます。
道具をそろえ始めるとコストが高くなる
そして、本格的にアナログで絵を描こうと思うのであれば、そのコストはどんどん高くなってきます。
紙と鉛筆でクロッキーやデッサンをしてるくらいならさほどでもありませんが、「色を塗ろう」と思った途端に追加のコストが大きくなってきます。
一番手を出しやすい水彩でも絵の具にパレット、筆洗、筆などを買いそろえると千円から数千円程度の出費になるでしょう。
コピックなどのマーカーも必要な色を何本も買いそろえればすぐに数万円単位の出費になります。
油絵などはいったいいくらかかることやら…。
アナログは初期費用の安さは大きなメリットですが、本格的な作品を作ろうと思った場合に非常に大きな追加コストを支払う必要が出てきます。
結果的にはデジタルの方が安くつく場合もあるでしょう。
初心者の絵の練習に向いているのは?
ここまでデジタル作画ツールとアナログ作画ツールのメリットとデメリットを見てきましたが、その上で、初心者により適した作画ツールはどちらだと言えるでしょうか。
初心者が絵の練習を始めるなら圧倒的に「アナログ」
初心者に適した道具は圧倒的に紙や鉛筆などのアナログ作画ツールでしょう。
特に絵の練習を始めるのならアナログがおすすめです。
これは上記のメリット、デメリットの項目でも述べていますが、非常に初期コストが安くて始めやすく、万一やめてしまった場合でも特に後悔するところがありません。
「自分には向いてなかったな」で済みます。
また、紙に描くので自分の描いている絵の全体像が把握しやすく、デッサン等の間違いに気付きやすくなり、絵を見る目の力が育ちます。
絵を見る力は、言いかえれば画力です。
何が間違っているのかに気付くことができれば、そこを修正することができます。
その段階では修正できなくても、ああでもないこうでもないと色々描いて試行錯誤している内に目の力がついて来ます。
初心者の人が絵の練習を始めるのであればアナログで始めるのがよいでしょう。
作品を作るのであれば「デジタル」
ある程度絵を描くということに慣れて来て、本格的に作品を作る段階に入れば、デジタル作画ツールの導入を検討しても良いかもしれません。
絵を描く力と知識が身についていれば、機能の多いデジタルツールもあまり問題なく使いこなすことができるようになるでしょう。
多彩なデジタル作画ツールの機能を使えば、手間をかけずに作品制作に臨むことができます。
要点まとめ
最後に今回の要点をまとめておきます。
デジタルの作画ツールにも、アナログの作画ツールにも、それぞれ道具としてのメリット・デメリットが存在します。
どちらも絵を描く優れた道具であることは間違いないので、自分の目的に合わせてより最適な道具を使うのが良いでしょう。
それでは、また次回。
▼今回の記事が少しでも勉強になったようでしたらクリックお願いします!
にほんブログ村